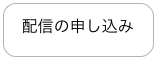現在、北陸先端科学技術大学院大学で日本語を教える本田弘之さん。実は、大学時代の専攻は、日本語ではなくて、地理学・文化人類学でした。世界中を旅して、いろいろなものを見て、さまざまなものを食べてきた、という本田さんのGochiは......。
*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
料理で「異文化理解を理解」した瞬間
*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
「日本語教員」(正確にいうと「自分の母語を外国人に教える教員」ですね)という仕事のおもしろさの一つは、世界のいろいろなところで仕事ができることだと思う。同じ「外国語教員」といっても、(日本人の)英語教員は、基本的に英語圏の地域にしか行く必要がないから「海外経験はイギリスとアメリカ合衆国だけ」なんていう人がめずらしくない。それに比べると(日本人)日本語教員の活動範囲はとても広い。
わたしも、立て続けにモンゴル、新疆ウイグル自治区、キルギスという3つの場所で仕事をするチャンスにめぐまれたことがある。この3つの場所は、ユーラシア北部に広がる大草原地帯にあって、モンゴル語やテュルク(トルコ)語を話す人たちが暮らしている。彼らは13世紀(中国では「元」の時代)に、ユーラシアの3/4を支配下においた遊牧騎馬民族の子孫にあたる人たちだ。
遊牧民族の「ごちそう」は、羊と決まっている。どこでも日本から来た日本語の先生をもてなすために、盛大に羊料理がふるまわれた。日本人は、あまり羊肉に慣れていないので敬遠する人も多いようだが、わたしは北海道出身なのでソウルフードはジンギスカン。だから、羊料理は大歓迎だ。
ただ、羊が大好きというわたしも、ちょっと苦手なのが羊の頭。羊の調理法は、テュルク系は焼肉、モンゴル系は塩ゆで肉が基本なのだが、どちらも大皿の中心に必ず恨めしそうに眼を閉じた羊の頭が載せられてくる。しかも、この頭が接客に重要な役割を果たす。
キルギスでは、主客と主人が片目ずつを分けあって食べることによって友情を確認するのだ、といわれ羊の眼球を一個食べるはめに......。という話をウイグルでしたら「ウイグルでは耳です!」と告げられ片耳を。さらにその二つの話をしたモンゴルのゲルでは「そうですか! モンゴルでは鼻です!」といわれて消しゴムみたいな食感の鼻を食べるはめに(もしかすると冗談だったのかも......。)
羊はおいしいんだけど、腿肉とスペアリブだけ持ってきてほしい。頭なんかつけてくるなよなー、と思いながら日本に帰ってきたある日、当時(1995年ごろです)、活躍しはじめたモンゴル人力士へのインタビュー記事が目に入った。
「日本料理で苦手なものはなんですか?」
「魚の頭です。目がこわいです」
彼らには、尾頭付きのタイのお造り(についてくる頭)がものすごく気持ち悪く、来日当初はそれが許せなかったらしい。
タイの頭をとってしまうと、せっかくのおもてなしの価値がなくなってしまうという日本人の感覚と、「羊の頭を見せないとおもてなしにならない!」と考えるモンゴル人(遊牧民)の感覚が見事にシンクロしていることを知り「異文化理解とはこういうことか!」と体得した瞬間でありました。