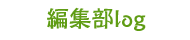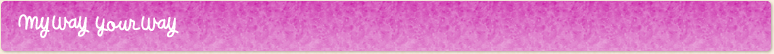Dance with Life
vol.1
もっと自由に踊りたい
大前光市、大阪府在住
2016.12

©劉成吉
大前光市さんは14年前、酔っ払い運転の車にひかれ、左足の膝から下を切断した。それは、憧れのダンスカンパニーのオーディションを受けるため、新潟に向かう前夜のことだった。しかし、それは彼にとって絶望ではなかった。その後訪れる大きな挫折と絶望を乗り越え、プロダンサーとして舞台に立つ。
希望の前夜に
救急車で運ばれ、痛みで意識がもうろうとするなか、医者から言われた。
「足を切ります」
この人はいったい何を言っているんだ? 意味がわからなかった。わかりたくもなかった。ぼくはずっと焦がれてきた金森穣さんが率いるダンスカンパニー「Noism」に入るはずなんだ。
目が覚めて足を見ると、短くなった左足の膝辺りがバスケットボールぐらいに腫れあがっている。激痛が走る。でも、新潟に行かなきゃいけない。たとえオーディションを受けられなくてもアピールしなきゃいけないんだ。そう思って車椅子で行こうとしたが止められた。包帯には血がにじんでいた。でも、どうしても行きたかった。
このときはまだダンスカンパニー「Noism」の一員になれると信じていた。どうやったら、「Noism」という目的地にたどり着けるのか、そればかりを考えていた。4ヵ月後、ようやくできあがった義足をつけた。スキー靴を履いているような感覚だったが、普通に歩ける。そして、スタジオに行き、いつものように練習をしようとした。しかし、思ったように動けない。以前なら目をつぶってもできていた踊りができない。ジャンプをすると、思いっきり転んだ。想定外だった。5回めに転んで、「今日はもう踊れない」と思ったとき、四つんばいになったまま泣いていた。もう立ちたくなかった。人前で泣いたのはこのときだけ。大きな挫折感、絶望を初めて感じた。

生活用の義足。初めての義足もこのような形態だった。
©劉成吉
前に進む

パーツを取り寄せては何回も作り直していきついた義足。この義足でバレエも踊る。
©劉成吉
それでもぼくは「Noism」に向かって進むことしか考えられなかった。お金ならいくらだって払うし、何だってやるから、ぼくはあの世界に戻りたいし、絶対に戻るぞ、そう思っていた。目的地に行くための最短ルートがなくなっても、どのルートだったら行けるのかを考えた。義足をできるだけ本物の足に近づければ、元のダンスができるはずだ。義足を改良すればいい。
初めて踊ったときにひっかかったのは足首から下。つま先が伸びないダンスなんてぼくにはありえなかったけれど、こうじゃなきゃだめだという思い込みをやめた。思い切って足首から下を切ってもらったのだ。ひとつの決断だった。
1ヵ月後、足首から下のない義足で踊ってみた。やはり踊りやすい。きれいなダンスだとは思わなかったが、目的地に一歩近づいた気がした。その後も、いろんなパーツを取り寄せて、どう組み合わせてどう加工したら、もっと踊れるようになるのかを考えては、義足技師に頼み込んで、何本も何本も作ってもらった。今のような形に行きつくのに8年かかった。
大きな絶望
「Noism」のオーディションは毎年受けていた。最初は穣さんも応援してくれていた。でも、5年目だったか、穣さんから「きみはNoismのダンサーにはなれない」ときっぱりと言われた。夜行バスを待つ2、3時間、涙があふれた。泣きながら、浮かんでくるのは「いったい今までの自分は何だったんだ」。穣さんのダンスを初めて見たとき、すぐにそのダンスに恋をした。何年もそのダンスをめざして猛練習をしてきて、その挙句に失恋。自分の存在を全否定された感じすらした。
ぼくの足は、ほかの人たちと同じ時間を踊るのは難しい。長く踊っていると激痛が出てきて、結局踊れなくなる。みんなと同じように毎日レッスンに参加して、リハーサルをする持久力はない。カンパニーについていけないことははっきりしていた。足がないことはかっこ悪いと思っていたので、足がないことをできるだけ見せないように、「足があるダンサー」と同じように踊ることばかり考えていた。でも、ぼくには足がない。「足があるダンサー」として、あの世界に戻ることはできないことが、穣さんに宣告されてようやくわかったのだ。
では、どうするのか。自分ができる動きを自分でつくっていくしかない、そう気持ちを切り替えた。プロとして魅力的なダンサーになって、お客さんを集める人になろうと決めた。これが新たな目的地になった。といいながら、かっこ悪い自分を受け入れるのに1年かかった。劣等感を抱えて、自分の動きを模索しながら前に進むしかなかった。

©劉成吉
未来が見えない

義足をつけないで踊るときには、お椀の形をしたものをつける。「大前ダンス用」と呼んでいる。
©劉成吉
事故にあってからの約10年間、生活のためだけに小銭をかせぐ日々だった。事故前はバレエで仕事がけっこうもらえるようになっていたが、その収入源が一切断たれたわけだからアルバイトをいくつもこなすしか方法がなかった。いろんなアルバイトをやったが、大体は立ちっぱなしだったり、肉体労働だったり......。義足にも慣れていなかったから、出っ張った骨が当たって痛くて何回も義足を脱いだ。常に身体のどこかをつねられた状態で生活しているようなもので、ずっと痛みに耐えていた。ダンスの練習は毎日していたが、将来については何も考えられない、そんな日々だった。
哀れみはいらない
たまに声がかかって舞台に立つ機会もあった。何よりも辛かったのは、たくさんのダンサーといっしょに舞台に立った後、ほかのダンサーはギャラがもらえるのに、ぼくがもらえるのはギャラではなく「お礼」。わずかな金額だった。義足のダンサーは人に感動は与えられたが、ギャラを与えてはもらえなかった。ほしいのは哀れみじゃない。障がい者なのに頑張っているね、ということばなんかいらない。ダンサーとして見てほしい。 それでも、ぼくにまだ技術が足りないからだ、もっとうまくなったら同じ金額のギャラをもらえるはずだ、そう思っていた。
自分を信じる
そういう状況だったが、自分は目的地に行くんだ、行けるんだ。そう信じ続けた。どんな形に変わってもそこに行くことが大事なのだ。変化することを受け入れてきた。こういうダンサーになるはずではなかったから、不本意ではあった。でも、どんな形でもいい、絶対にプロのダンサーになってやる。だから、義足も改良するし、足に負担をかけないで踊るために、身体の動かし方を研究し、さまざまなダンスを習いに行った。ストリートダンス、ジャズダンス、モダンダンス、日本舞踊......。武道も習った。必死だった。それでもまだどこかで障がい者のダンサーとして見られるのはいやだった。
義足をはずして踊る

「目覚めよと叫ぶ声が聞こえる」のときの衣装。いちばん好きな衣装だ。
©劉成吉
2012年頃に舞踊家、佐藤典子さんに出会った。義足をはずして踊ったらどうか、そういう作品にするから、と彼女は言った。ダンスのタイトルは「足のないカナリヤ」。ぼくはダンス一つひとつの動きが何よりも大事だと思っていたが、佐藤先生は作品全体のストーリー、構成を大事にする。
義足をはずして踊ってみると、動きやすいし、何よりも痛みから解放された。そして、自分の可能性が広がったように感じた。自分の魅力をどう表現するか、そのヒントをもらったのだ。
その後、義足をつけないで踊った「目覚めよと叫ぶ声が聞こえる」は自分らしい作品になった。また、作品の役によって義足も替える。例えば、ピエロなら、右足よりも長くなる義足を使う。
近づくと遠ざかる
最近、義足のダンサーと呼ばれなくなってきた。いろいろなトレーニングを積んで普通の人と同じ動きができるようになってきたからだと思う。それは自分がめざしてきたことでもあったが、皮肉なことにそうなると限界が見えてくる。結局、足があるダンサーにぼくはなれないのだから。
じゃあ、どうしたら魅力的なダンスができるのか、自分の可能性を生かせるのか。義足であることを活用したほうがいいと思うようになった。義足であることもすべてを含めて自分の魅力にして、それを見たいと多くの人が思ってくれれば、そのときにプロのダンサーになれるのだと思う。
自分にしかできないダンス
自分にしかできない、こういう足の人にしかできないダンスをしたい。今は、義足で踊ることすらどうなのかなと思い始めている。義足をつけるということは普通の人を追いかけているわけで、この時点で負けているのではないかと思うのだ。
だから、リオデジャネイロ・パラリンピックの閉会式では、義足をつけないで1本足でバク転をしたいと思った。しかも人をあっと驚かせるために4連続することにこだわった。これができれば、障がいをもっている人に対してみんなが一目置くようになるんじゃないかと思ったのだ。
閉会式では世界の人たちに、バク転だけでなく、ダンスを見てもらえた。何かを感じてもらえたのではないか。
もっと自由に
ぼくはプロフェッショナルとして、自分がいちばん素敵に見える動きをつくっていきたい。踊りを通じて自由になりたい。自分が思い描くダンスをすることで自由になれる。もっともっと自由になりたい、自由になれると思う。不自由な時期が長かったから、人一倍、自由に対する思いは強い。身体を改良することで、自分が思い描く動きがもっとできるようになる。
そもそもダンスとの出会い

©劉成吉
中学2年生のときに、3年生を送る会で演劇を舞台ですることになった。中学生は、目立つことをなかなか率先してやりたがらないものだ。クラスメートから「やれよ」と言われ、準主役を演じた。小道具を自分なりに工夫してやってみた。本番では大きな拍手。気持ちよかった。そして何よりも、小学生のときからぼくをいじめていたやつらの態度が明らかに変わった。
「ぼくが輝ける場所はここだ!」
舞台に立つ仕事をしよう。そう思った。

お気に入りのくまモンの帽子とTシャツで。自分のブログにアップしている動画には、くまもんの帽子を被って登場することが多い。
©劉成吉
華麗な世界への憧れ
ミュージカル俳優になることを夢見て、演劇部のある高校に進学し、アルバイトをしながらバレエを習い始めた。バレエに夢中になった。華やかなバレエの世界への憧れもあった。
父は建設現場で働いていて、いつも汚れた作業着で、軍手をはめて、材木を中古の軽トラックに積んで仕事に出かけていく。ずっとカッコ悪いと思っていた。こんな世界なんかいやだと思っていた。
無様でもいい
車に轢かれて病院に運ばれたとき、家族が飛んできてくれた。もちろん父も。父が「大丈夫、お前は大丈夫だ」と言いながら、ぼくの右手を両手で握った。グローブのようにごつくて、がさがさしていて汚い手だった。なのに、安心感があった。父はぼくの味方だ。「俺は大丈夫。生きていく」と父と約束したのだった。
父の生き方は無様だったかもしれない。でも強い。ぼくも無様でも生きていける。無様でもダンスを続ける。そう思った。
ダンスには反対だった父も、ぼくがずっと続けているのを見て、認めてくれるようになった。
それからもがき苦しんできてプロダンサーになった今、父が無様だったと思わないし、自分も無様だとは思わない。無様だと思う人がいたとしてもかまわない。
ぼくは人一倍負けず嫌い。いつか見返してやる、という思いでずっとやってきた。
みんなどんどん変わっていっていい。ぼく自身変わってきた。それまで自分が思ってきた「美しい」ものも、自分の狭い好みの話でしかない。美しいものはいっぱいある。まず自分の美しさを知らなくてはいけない。ぼくの場合は、足がないことだ。
今、楽しくて仕方ない。ぼくはもっと自由になれる。そういう確信があるから。
足があったときとは違う身体の使い方もできるようになって、前よりも身体の使い方がうまくなった。
ぼくは、ダンスで自分を表現できるのだ。
インタビュー:2016年10月
構成:TJF